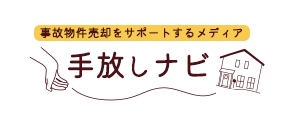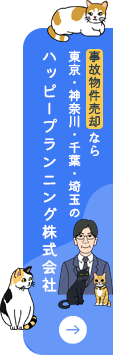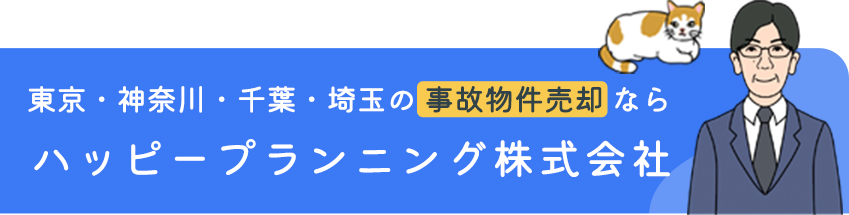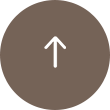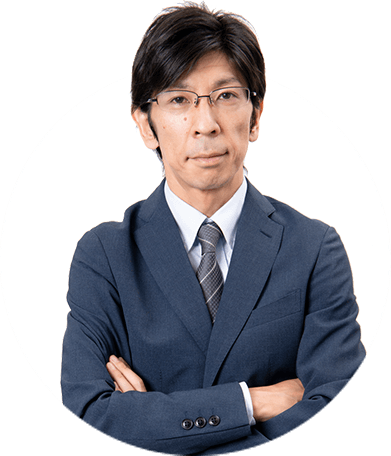近年、社会問題となっている「孤独死」。一人暮らしの高齢者を中心に孤独死は増加しており、発見が遅れるケースも少なくありません。
親族がいない、あるいは関係が希薄な場合、遺体の引き取りを巡る問題が生じることも。
そこで本記事では、孤独死した方の遺体の引き取りを拒否できるのか、その際の手続きや注意点について解説します。
孤独死による遺体の
引き取り拒否は可能
結論から言うと、法律上、遺体の引き取りを拒否することは可能です。遺体の引き取り義務は、法律で明確に規定されているわけではなく、民法上の親族関係に基づく道義的な責任に過ぎません。そのため、親族が遺体の引き取りを拒否した場合、自治体が対応することになります。
ただし、地方自治体によって対応が異なるため、拒否したからといってすぐに全ての責任が免除されるわけではありません。自治体が引き取る場合でも、火葬費用の請求が発生する可能性もあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
遺体の引き取りを拒否する
際に行うこと
1.自治体へ相談する
まず、故人が居住していた自治体に連絡し、遺体の引き取りを拒否したい旨を伝えます。
多くの自治体では、遺体の引き取りを拒否された場合は行政が火葬・埋葬を行う制度を整えています。
2.拒否の意思を明確にする
親族としての関係性がある場合、自治体から引き取りを求められることがあります。
自治体によっては引き取り拒否について書面での提出を求められる場合もあるため、指示に従い対応しましょう。
3.費用負担の有無を確認する
自治体が火葬や埋葬を行う場合でも、親族に費用請求がされることがあります。
特に経済的に余裕があると判断された場合は負担を求められることがあるため、事前に確認し、必要に応じて費用免除の申請も検討しましょう。
4.相続放棄の手続き
相続放棄をする場合、故人が亡くなったことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行う必要があります。
これにより、故人の財産だけでなく、借金などの負債も相続しないことになります。
遺体の引き取りと
相続の関係
遺体の引き取りは相続とは異なる問題です。遺体は財産として扱われないため、引き取りを拒否したからといって自動的に相続放棄が成立するわけではありません。
そのため相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
まとめ
孤独死した方の遺体の引き取りは法律上の義務ではないため、拒否することは可能です。
ただし、自治体ごとに対応が異なり、場合によっては火葬費用の請求が発生するため、事前に確認することが重要です。また、遺体の引き取り拒否と相続放棄は別の問題であり、相続放棄を希望する場合は家庭裁判所での手続きが必要です。
孤独死が社会問題となる中、事前の対策や制度の理解が求められています。親族として適切な対応を取るためにも、自治体や専門家へ相談しながら進めていくことが望ましいでしょう。