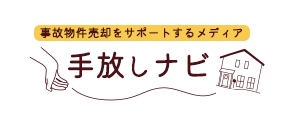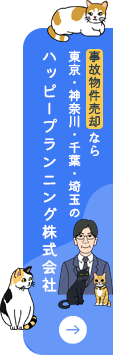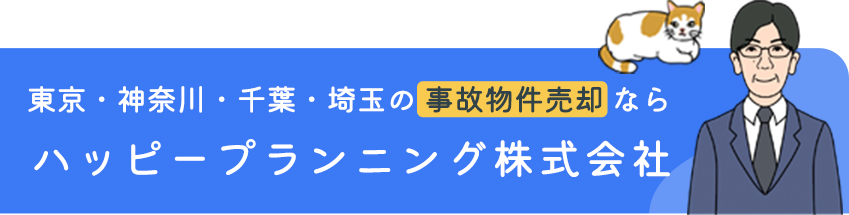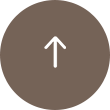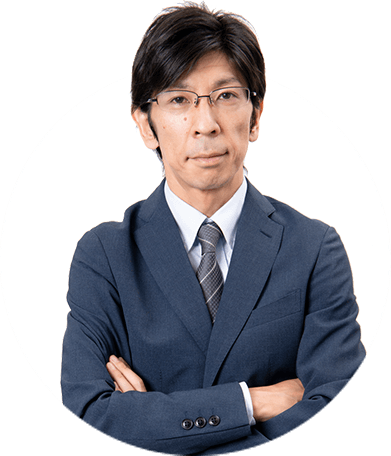事故物件にはさまざまな遺品が遺されるケースがあり、そういった場合には遺品整理の問題が必ずつきまといます。しかし遺品整理は遺族でなければできず、「貸していた部屋で入居者が亡くなった」「相続した物件が事故物件だった」などその状況によって対応方法が異なります。
事故物件の「遺品整理」とは?
遺品整理の法的位置づけ
遺品整理は法的には「相続財産を整理する行為」と位置づけられています。相続人が遺産を相続する代わりに遺品整理を行い、財産や債務を確認する責任を負うことになります。遺言書がない場合、法定相続人が遺品整理を行うのが一般的とされています。
特殊清掃との違い
遺品整理と特殊清掃はどちらも人が亡くなった後に部屋を片付ける作業をいいますが、その目的と作業内容に違いがあります。遺品整理は故人の遺品を整理・処分することが目的ですが、特殊清掃は遺体の発見が遅れたことなどにより汚染された部屋の清掃や消臭・除菌を行うことが目的となります。
相続人とオーナーの責任範囲(勝手に処分してよいか?)
相続人は故人の遺品を整理し財産や負債を把握する責任がありますが、賃貸物件の場合には連帯保証人にも責任が生じる可能性があります。一方でオーナーは遺品整理を行う権利は持っていないため、相続人不在時には行政などと連携を取り適切な対応を図らなければいけません。
原状回復や再貸出しとの関係性
遺品整理における原状回復と再貸出しは賃貸物件の場合に特に関連性の高い要素とされます。遺品整理によって生じた家財道具の処分や部屋の清掃に関しては、原状回復義務の一環として行われることが一般的です。
ケース別!事故物件の遺品整理の流れ
遺品整理は遺族が行うものなので、物件と故人との関係によって対応の流れが変わると紹介 h3でケースごとの流れを紹介して下さい貸していた部屋が事故物件になった場合
まず前提としてですが、遺品整理は遺族が行わなければいけません。そのため物件と故人との関係によって流れが変わるという点は認識しておきましょう。そのうえで貸していた部屋が事故物件になった場合ですが、まずは警察の捜査に始まり相続人への連絡を行います。その後は原則として遺族が遺品整理を行うことになりますが、遺族に連絡が取れないケースや相続放棄をされた場合にはオーナーが行政などと連携を取りながら対応することになります。
事故物件を相続した場合
上記はオーナー目線の話ですが、反対に「事故物件を相続した場合」にはどうすればよいでしょうか。実際の手続きとしては相続協議を経て登記、遺品整理という流れになります。登記前における遺品整理は相続人全員の同意がないとできませんので、非常に煩雑で面倒になります。
遺品整理を依頼する際の専門業者の選び方
遺品整理士・特殊清掃士の資格
遺品整理士は遺品整理に関する専門知識や遺族への対応、法律に関する知識などを持ち、故人の遺品を適切に整理・処分する知見・ノウハウを有していると証明できる専門家です。一方の特殊清掃士は、孤独死や事件現場などで発生した汚染・異臭を除去し、衛生的な環境を回復させるための知見やノウハウを有していると判断できる専門家です。
法令順守・損害保険加入の確認
遺品整理における法令遵守とは、遺品整理業者が業務を行う上で、廃棄物処理法や古物営業法などの関連法令を遵守することを指します。ほかにも損害保険に加入しているかなど、「ちゃんとしている業者」かどうかを確認するとよいでしょう。
実績・口コミ・料金体系の見方
ホームページで実績が紹介されているか、口コミの件数や評点がどういった状況にあるかを確認するとよいでしょう。また、料金体系については明確に示されているかどうかをしっかり確認しましょう。
まとめ
所有している物件が事故物件になるという経験はそうそうあるわけではないので、いざその状況になってしまうとどうしていいかわからなくなるでしょう。事故物件の対応はぜひプロへの相談を検討してみてください。