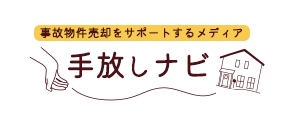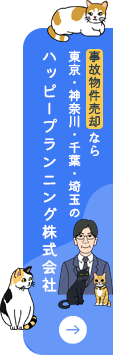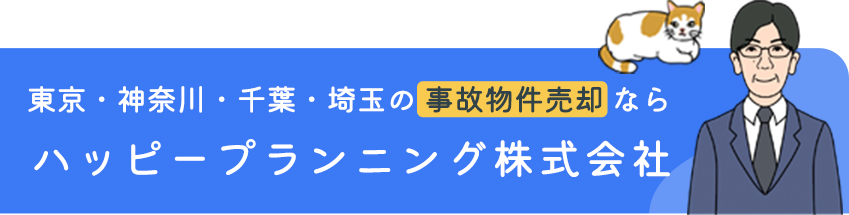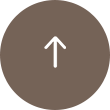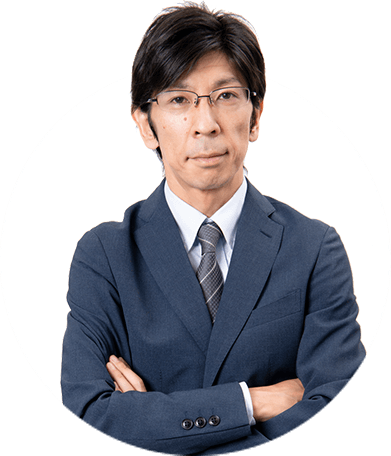事故物件を売却する際には、告知義務があります。しかし、すべての事故物件が告知対象になるわけではありません。ここでは、事故物件の定義や告知義務が発生するケース、告知が必要な期間などの注意点、告知を怠った場合のリスクを解説します。
事故物件とは?
事故物件とは、特に「心理的瑕疵」がある不動産のことを指します。心理的瑕疵とは、見た目や設備に問題はなくても、住む人が心理的に抵抗感や嫌悪感を抱く欠陥のことです。具体的には、物件内で自死や他殺、孤独死などの人の死があった場合があります。隣に暴力団の事務所や宗教施設、火葬場など「環境的瑕疵」がある物件も事故物件です。事故物件は入居者に心理的負担を与えるため、契約時には告知義務が課されています。
事故物件の告知義務とは?
法律的根拠を解説
事故物件の売却や賃貸を行う際、売主や貸主には買主や借主に対して事故の事実を伝える「告知義務」があります。これは契約締結前に重要事項説明の一環として行う必要があります。
告知義務の根拠は、宅地建物取引業法(第47条)や国土交通省ガイドラインに基づいています。事故物件に該当する事実を告知しなかった場合、契約解除や損害賠償請求の対象となる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」[PDF]
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)
告知義務の適用範囲と期間
告知義務の範囲や期間については、2021年に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によって、一定の基準が示されました。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」[PDF]
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)
告知が必要なケース
自死・他殺が発生した場合(室内で発生した場合は原則告知が必要)
賃貸を予定している部屋内において、過去に入居者が首つり自殺をした、などのケースでは、原則として告知義務が生じます。自殺だけではなく他殺も同様です。自殺・他殺がその室内で発生したことがポイントです。
事件性のある死亡事故が発生した場合
賃貸を予定している部屋内において、例えば暴行により人が死亡した場合、その事件は刑事事件として取り扱われ、「事件性のある死亡事故」として告知義務が生じます。
特殊清掃(遺体の腐敗処理など)が行われた場合
何らかの理由により部屋内で人が死亡し、その後、遺体の腐敗が進み専門業者による特殊清掃が必要となった場合、新たな入居者に対して事故物件であることを告知する義務が生じます。
物件の売買をする場合
事故物件を売買する場合は告知が必要です。告知義務には時効がなく、事故から何年経っても解除されません。これは売買契約が賃貸契約と比べて契約金額が大きく、心理的瑕疵による買主の損害が大きいためです。さらに、物件を更地にしたり建て替えたりしても、過去の事故の告知義務は消えません。売主は売買の際に人の死など心理的瑕疵の存在を必ず買主に伝える必要があります。
告知が不要なケース
老衰や病死による自然死
例えば高齢の入居者が老衰や病気などの理由により就寝中に亡くなった場合、これは自然死として取り扱われるため、原則として新たな入居者に対する告知義務は生じません。老衰や病気による死亡は、ごく一般的な死亡理由であり、自殺や殺人事件に比べて入居者の心理的瑕疵も低いと考えられるためです。
共用部分(マンションの廊下やエントランス)で発生した場合
例えば、マンションの住人が共用部分(階段など)で転倒して死亡した場合、その死亡事故は部屋の中で発生したものではないため、新たな入居者に対する告知義務は生じません。
事件・事故が発生した日から一定期間(概ね3年)が経過した場合
事故物件とされた部屋であっても、事件・事故の発生から概ね3年経過すれば、基本的には告知義務が不要となります。ただし、近隣住民の心に残るような大事件が発生した部屋の場合、例外的に3年以上が経過しても告知義務が残り続けることもあります。
事故物件ロンダリングとは
「事故物件に誰かが1回住んだら、以後は新たな入居者に対する告知義務が消滅する」という考え方や取引を事故物件ロンダリングと言いますが、この考え方は明確な誤りです。事故物件ロンダリングを正当化する法的根拠はまったくありません。
告知義務が解除されるタイミング
心理的な負担が軽減されるまで告知義務は継続する
告知義務は心理的な負担が軽減されるまで続く
原則として、事故物件であることの告知義務は概ね3年です。この3年という期間の根拠は、入居者の心理的な負担が軽減されるまでに要する時間とされています。
ただし、当ページの一部でも触れた通り、すべての事故物件の告知義務は3年で消滅するわけではありません。近隣住民の記憶に強く残るような凄惨な殺人事件があった部屋などは、より長期間にわたり告知義務が残り続ける可能性もあります。過去には、約50年前に発生した凄惨な殺人事件が心理的瑕疵に該当するとされ、告知なく成立した売買契約の解除が認められた判例もあります(※)。
「心理的な負担が軽減される」ポイントとは?
事故物件に対する心理的な負担とは、言い換えれば、事件・事故があった同じ空間に住むことへの嫌悪感です。
心理的な負担が軽減される理由の一つだ時間の経過です。心理的瑕疵には「時間希釈の原則」があります。時間が立てばたつほど、当該事件・事故に対する近隣住民の記憶や印象が薄れ、少しずつ嫌悪感が弱くなっていくという考え方です。
この考え方に基づき、一般的な事故物件の告知義務期間は概ね3年とされていますが、上述の通り、全ての事例において3年で告知義務が消滅するわけではない点にも注意が必要です。
告知義務を怠った場合の
リスク
告知義務に違反すると「瑕疵担保責任」「契約不適合責任」を追及されます。具体的なリスクと罰則を確認していきましょう。
補修・代替物の引き渡し
事故物件の告知義務を怠ると、買主は「契約不適合責任」に基づき売主に対して補修や代替物の引き渡しを請求できます。民法第562条に規定されている追完請求権です。取引した物件が契約と異なる欠陥を有しているため、買主はその不具合の是正を求められます。心理的瑕疵に起因する事故物件の場合も同様。告知不足が原因で裁判になれば、売主は物件の補修ではなく、代替物を引き渡す義務を負う可能性があります。
売買・賃料の減額請求
事故物件の告知義務を怠った場合、買主は契約不適合責任に基づき、まず売主に履行の追完(欠陥の補修や代替物の引渡し)を請求しますが、多くの場合、心理的瑕疵は物理的な補修が不可能であるため追完は困難です。そこで買主は民法第563条の「代金減額請求権」を行使でき、履行の追完がなされない場合や拒絶された場合には、事故により下落した物件価値に応じて購入代金の減額を求められます。この代金減額請求により、買主は事故物件であることによる損失分を補償してもらうことが可能です。
損害賠償
事故物件の告知義務を怠った場合、売主は民法第564条に基づき損害賠償請求を受けるリスクが高まります。これは、売主の告知義務違反が契約の不履行や不法行為にあたると認定され、買主が被った精神的苦痛や経済的損害の補償を求めるものです。裁判例では、事故物件の心理的瑕疵を隠して売買契約を締結した場合、契約金額の半分を超える損害賠償が命じられたケースもあります。さらに、損害賠償には逸失利益や原状回復費用などが含まれ、違反の重大さによっては契約解除や訴訟費用の負担も発生します。
契約の解除
事故物件の告知義務を怠った場合、買主は民法第564条および宅建業法第35条に基づき、契約解除権を行使できます。これは、重大な心理的瑕疵を隠したことが契約不適合(債務不履行)にあたるためで、買主は告知されなかった事故の事実を理由に契約そのものを解除し、購入代金の返還を請求できます。契約解除が認められると、売主は移転登記費用やその他諸経費の返還、さらには損害賠償請求にも対応しなければならず、売買契約が白紙に戻る形となります。
罰金と懲役
事故物件の告知は、宅建業法上の「重要な事項」に該当します。宅建業法第47条では、宅建業者が故意に重要な事項を告げず、虚偽の説明をした場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科されるという厳しい罰則が規定されています。つまり、事故物件の告知義務違反は、宅建業法第47条により厳しく罰せられる可能性があります。売買取引に関わる宅建業者だけでなく、該当する売主や賃貸人にも適用される場合があるため、注意が必要です。
行政処分
宅建業者が事故物件の心理的瑕疵を告知しないなど告知義務を怠った場合、行政からの監督処分の対象となります。主な処分には「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」があり、違反の悪質性や損害の程度によって処分内容が決まります。例えば、重要事項説明義務違反では、指示処分から始まり、改善が見られない場合は最長1年の業務停止処分となります。さらに情状が重いと免許取消処分に至る可能性があります。業務停止処分中は宅建業に関する営業活動が禁止され、処分内容は公表されるため、業者の信用失墜にもつながります。
まとめ
事故物件の売却を考える際には、告知義務の範囲や法律を正しく理解することが重要です。
特に、2021年のガイドラインによって告知義務の明確な基準が示されたため、それに従って適切に対応することが求められます。
事故物件の売却に関する不安がある場合は、専門家に相談しながら進めることで安全かつスムーズに売却が進められます。