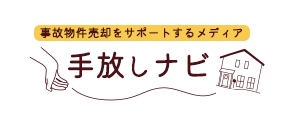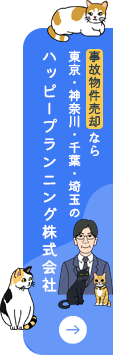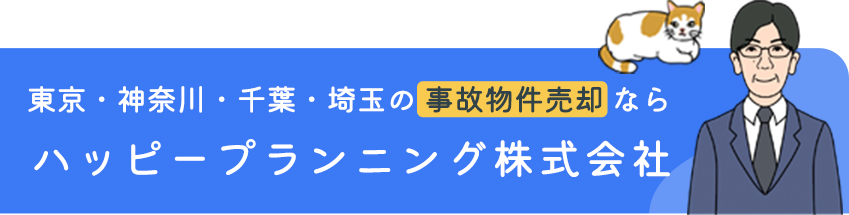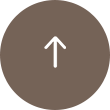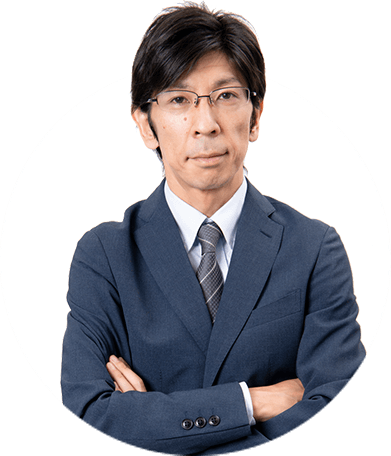
『ハッピープランニング株式会社』代表
相談実績が豊富な、
事故物件対応のプロフェッショナル。
事故物件は売却が困難だと思っている人も少なくありませんが、事故物件も売却が可能です。ただし、売却金額は相場より安くなる可能性があります。また、告知義務など、手間がかかることも。ここでは、マンションが事故物件とされるケースや事故物件を売却する際のポイントを解説します。
マンションが事故物件と
されるケースとは?
マンションが事故物件とされるのは、自殺・殺人・事故死・重大な事件などが発生し「心理的瑕疵」がある場合です。自室での事故があった場合と共用部での事故があった場合があります。自室での事故の場合、原則として告知義務が課せられます。一方、隣室や上下階での事故については、告知義務はありません。ただし、エレベーターなど利用者の多い共用部で事件・事故が発生した場合には告知が望ましいとされています。ワンルームや単身用マンションは部屋の広さや構造上、心理的影響を強く受けやすい傾向があります。
事故物件(人の死)の定義
人の死に起因する心理的瑕疵が存在すると判断されたマンションは、事故物件と認定されます。自殺や他殺はもちろん、事故死や自然死であっても特殊清掃が実施されたケースは事故物件の対象です。
国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、事故物件の範囲や告知期間が明確化され、取引判断の基準として広く活用されています。
事故物件になると、「告知義務」が発生します。国土交通省のガイドラインでは、「自然死や不慮の事故死以外の死」や「特殊清掃が必要な死」があった場合に告知義務が生じるとされています。告知義務があるだけで、売却自体は可能です。ただし、買手が付くかどうかは別問題です。賃貸の場合の告知義務期間は原則約3年ですが、売買には明確な告知義務の期間規定がなく、長期にわたり告知が求められるケースもあります。告知義務を怠ると、売主は民法上の「瑕疵担保責任」や「契約不適合責任」を追及される可能性があるため、注意が必要です。買主が物件の事故歴を知らされなかったことによる損害賠償請求などのトラブルに発展するため、不動産取引では正確な告知が重要です。
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)
(https://www.jikobukken-tebanashi.com/knowledge/disclose.html)
マンションの事故物件の告知義務を怠った場合のリスク
補償請求
告知義務を怠ると、買主が被った不利益について、売主は補償を求められる場合があります。具体的には、原状回復費や追加広告費、再募集にかかる実費などが対象です。金額の妥当性については、領収書や見積書といった証拠資料により判断されることになります。
減額請求
事故物件である事実が告げられなかった場合、買主や借主は市場価値との差額分を減額請求することが可能です。心理的瑕疵による価値の低下が客観的に認められた場合には、周辺の相場や査定結果をもとに価格調整が行われることとなります。
損害賠償請求
告知を怠った結果として契約者に経済的損害が生じれば、売主は買主から損害賠償請求を受ける恐れがあります。損害賠償には再契約にかかる費用や引っ越し費用、弁護士費用などが含まれる可能性があるほか、故意や過失の有無、損害との因果関係も考慮されることとなります。
契約解除
事故物件である事実を隠して売却した場合、売買契約の目的が達成できないと判断されて契約が解除される可能性もあります。買主や借主が事実を知っていれば契約しなかったと認められる場合に適用され、契約が解除されれば原状回復や代金返還の手続きが必要となります。
共用部での事件は告知義務対象外
マンションの共用部での事故については、原則として告知義務はありません。共用部分の事故が専有部分の契約判断に大きな影響を与えないとされるためです。しかし、社会的にインパクトが大きい事件やニュースで報道された場合は、購入希望者や入居希望者に知られてしまうことが多く、心理的な影響を考慮すると告知が望ましいケースもあります。また、エレベーターやエントランスなど利用頻度の高い共用部での事故の場合にも注意が必要です。告知しない場合でも、誠実に対応しないと損害賠償請求のリスクがあるため、状況に応じて適切に伝えることが求められます。
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/3_17.pdf)
マンションの事故物件の
売却相場
事故物件のマンションの売却相場は、資産価値の5〜9割ほどになります。
例えば、4,000万円の価値を持つマンションの場合、売却価格の目安は2,000〜3,600万円です。
売却相場は、事故物件となった原因により異なります。孤独死は資産価値の1〜2割ほど低下する一方、他殺は3〜5割低下する場合があります。
事故物件となったマンションを売却するポイント
特殊清掃・リフォームで綺麗に
事故物件の売却では、特殊清掃やリフォームを行い、室内をできるだけ綺麗に保つことが重要です。事故現場の清掃だけでなく、床・壁・天井などを新しく交換し、印象を改善することで買い手の心理的抵抗を和らげられます。また、全体的なリフォームや外観の修繕もおすすめです。特にワンルームなど狭い部屋は内装が重要視されます。
一定の期間を空ける
事故や事件発生直後から時間を置くことが効果的です。直後は物件のイメージが強く、買い手が見つかりにくいため、数年程度の期間を空けて心理的抵抗を和らげることが望ましいとされています。ただし、売買の場合は期間を空けても告知義務は消えず、過去の事故についても買主に正確に伝える必要があります。期間を空けることで売却活動がしやすくなる一方、誠実な情報開示が重要です。
一棟マンションなら更地にするのも手
一棟マンションが事故物件となった場合、建物を解体して更地にする方法も有効です。事故や事件のイメージが強い場所は、清掃やリフォームだけで印象を払拭しづらいため、建物を取り壊して土地として売り出すことで買い手が付きやすくなることがあります。ただし、更地にしても事故の告知義務は消えず、解体費用や固定資産税の増加も考慮が必要です。速やかな売却や別の土地活用も視野に入れましょう。
事故物件の買取業者に依頼する
事故物件を早く手放したい場合、不動産買取業者に依頼するのが効果的です。買取業者は事故物件の特殊性を理解しており、迅速に査定・買い取りを進められます。長期間の販売活動が不要で、すぐに現金化できる点が大きなメリットです。また、引渡し後の契約不適合責任を免責にできることが多く、売主のリスク軽減にもつながります。ただし、相場よりかなり低い価格になる傾向があるため、早さを優先する場合に適しています。
マンションの事故物件の
売却事例
埼玉県S市の分譲マンション

築年数10年
殺人が起きた物件で事件から日も浅く、少し調べればマンションの外観も出てきてしまう状況。
しかし利便性の高い人気駅から徒歩10分圏内と、人気エリアにある物件でした。
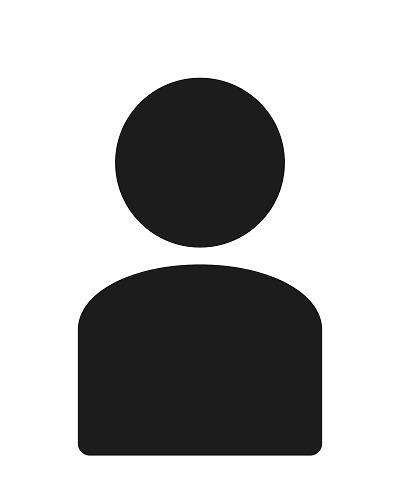
早く手放したかった
近親者による殺人が発生し、ニュースでも報道された実家を早く手放したかったです。
事故物件ではありましたが、立地は良いので複数社に査定を依頼し、最も早く室内確認と買取金額算出をした会社に決定しました。

ニュースにもなった物件でしたが、立地の良さから事件を上回るぐらいニーズがあると判断し、買い取り金額を算出しました。 今回は相続も遺品整理も済ませていただいていたので、とにかく物件の売買を早々に済ませました。
千葉県M市の分譲マンション

築年数25年
孤独死された場所がベッドの上だったため室内の損傷はほとんどなく、キレイな状態でした。
単身向けのお部屋で、交通の便が良い駅が最寄り駅です。
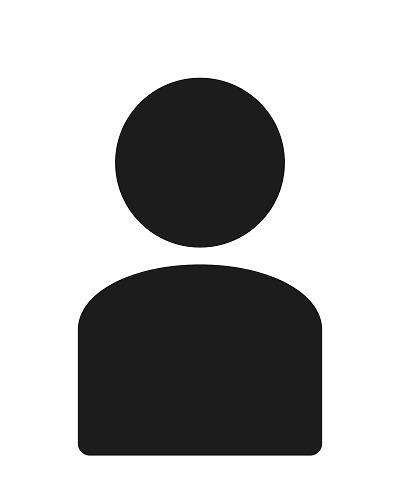
30代の娘が一人暮らしの自宅で孤独死し、突然の訃報に驚きと悲しみでいっぱいでした。
娘の部屋に入ることも辛く片付けもできませんでしたが、娘が自分で買った部屋のため売却しなければなりませんでした…。

お子様が一人で亡くなってしまったことがツラく悲しく、あまりお部屋には入りたくないとのことでした。一緒に最低限の確認だけした後に、片付けはこちらで請け負い、お部屋の状態から買い取り金額を算出しました。

事故物件の買取専門業者
「ハッピープランニング」

サポート
ハッピープランニングでは、ご遺族の悩みやプライバシーに配慮しながら事故物件の状態・状況に合わせた売却サポートを行っています。
代表の大熊昭氏は、これまで数多くのご遺族と向き合い、3,000件以上の相談にのってきました(※2025年4月1日調査時点)。
自社でのリフォームを検討するなど1円でも高く買い取りができるよう注力しています。
マンションの事故物件の売却に関するQ&A
Q.事故物件の売却に死亡診断書は必要ですか?
A.回答
事故物件を売却する際、死亡診断書の提出は法律上の義務ではありません。ただし、買主や仲介業者が死亡時期や死因を確認したい場合には、任意で提示するケースもあります。
根拠資料として開示することで取引の信頼性は高まりますが、個人情報保護の観点から、不動産会社と相談しながら慎重に扱うことが大切です。
Q.入居者が自殺した場合に損害賠償は請求できるものですか?
A.回答
入居者が自殺した場合、貸主は物件価値の低下や空室期間の発生など、経済的な損害を受けることがあります。そのため、原状回復費用や特殊清掃費、再募集までの家賃損失などについて、入居者の遺族や連帯保証人に損害賠償を請求できる可能性があります。
請求の可否については、契約書に明記された責任範囲や、入居者本人の行為と損害の因果関係により判断されることになるでしょう。
また、損害額を証明するには、見積書や請求書、入居記録といった客観的資料をそろえることも必要です。実際の請求は感情的な対立を招く恐れもあるため、弁護士など専門家を通じて慎重に進めることが望ましいといえます。
Q.遠方に住んでいて立ち会えなくても手続きはできますか?
A.回答
遠方に住んでいる場合でも、事故物件の売却手続きは不動産会社や代理人を通じて進めることが可能です。委任状と本人確認書類を提出すれば、現地確認や契約締結、引き渡しまで一任できるケースもあります。
郵送やオンライン手続きを活用すれば、立ち会いが難しい状況でもスムーズに売却を完了できるでしょう。