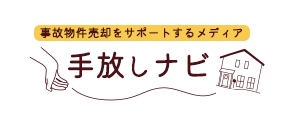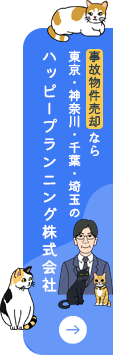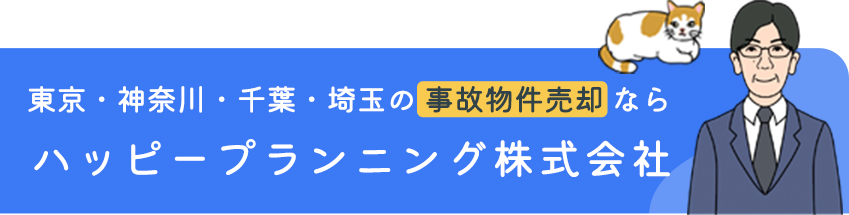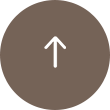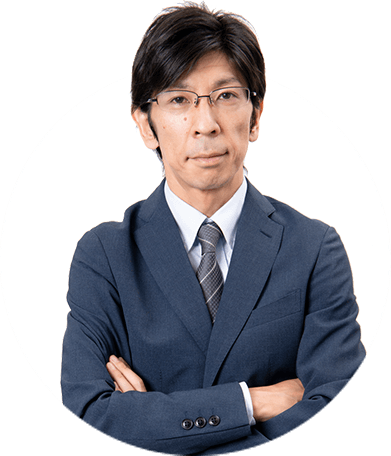所有しているアパートが事故物件になると、「もう売れないのでは?」と不安になるもの。しかしながら実際には、事故物件であっても売却は可能であり、適切な手順を踏めば買主が見つかるケースもあります。
ただし、売却価格は相場より低くなる傾向がある点、また告知義務など特有の手続きが必要になる点は理解しておきましょう。
アパートが事故物件とされるケースとは?
アパートが事故物件とされるのは、人の死が発生した結果、入居希望者に心理的抵抗を与える場合です。自室での自殺・他殺などのほか、事故死や自然死でも特殊清掃が行われた場合には原則として告知義務の対象となります。
隣室や上下階での死亡は通常、告知は不要ですが、エレベーターなど多くの人が利用する共用部での事件については、事案により説明が望まれることもあるでしょう。
特に単身者向けやワンルームでは影響が強く、事故物件は価格や成約率に響く可能性があります。
心理的瑕疵とは
心理的瑕疵とは、建物の構造や設備に欠陥がなくても、過去の出来事により入居希望者が避けたいと感じる要素が存在する状態を指します。自殺・他殺・孤独死・事故死などが、その典型例。室内において人の死が発生すれば敬遠の度合いが高まり、相場の下落や成約率の低下につながる可能性があるでしょう。
物理的瑕疵と異なり、心理的瑕疵は修繕によって解消できるものではありません。事故物件であることを前提に、適切な情報開示を通じて公正な取引を目指す必要があります。
事故物件になると「告知義務」がある
アパートが事故物件となった場合、売主や貸主には、買主・借主に対して事実を告知する義務が生じます。適切に告知し、買主・借主が納得すれば売買や賃貸に支障はありません。
告知が必要な期間は、賃貸であれば事故物件となってから3年間が目安。一方、売買には期間の定めがなく、死因や経過、社会的影響などの個別事情に応じて告知義務の期間が判断されることとなります。
告知が必要にも関わらず怠った場合、売主・貸主は契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を根拠に、損害賠償や契約解除、減額請求等を受けるおそれがある点にご注意ください。売却・賃貸に際しては、不動産会社と情報整理を行い、国土交通省のガイドラインを参照しながら適切なタイミングで必要な情報を開示することが望まれます。
参照元:国土交通省[PDF](https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)
共用部での事件は告知義務対象外
アパートの廊下や階段など、入居者が共有で利用する場所で発生した事故については、原則として告知義務の対象外とされています。実際に東京地裁の判決(平成18年4月7日)では、共用部で起きた自殺事件について「告知義務なし」と判断された例もありました。
ただし、社会的に注目を集めた事件や地域の評判に強い影響を与えた事件などの場合は、例外的に説明が求められることもあるでしょう。共用部での事案でも、周囲の認識度によって対応が異なる点に注意が必要です。
出典:東京地裁 平成18年4月7日
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/3_17.pdf
告知義務を怠った場合のリスク
補償請求
契約後に事故の事実を知った買主から、修繕費や仲介手数料、その他の費用の返還を求められることがあります。双方で見解が食い違えば、紛争に発展するおそれもあるでしょう。。
減額請求
買主が「事故物件であるなら価格が低くなるはず」と主張し、売買代金の一部返還を求める場合もあります。結果として、買主は当初想定した売却益を確保できない可能性が高まります。
損害賠償請求
事実を隠して契約した場合、買主から損害賠償を請求されるおそれがあります。心理的瑕疵を巡る裁判では、慰謝料や引っ越し費用の支払いを命じられることも想定されます。
契約解除
買主が「取引の前提が崩れた」と判断すれば、契約の解除を求めてくる可能性があります。売主にとっては再販売の手間や価格の下落など、大きな損失につながるリスクが残るでしょう。
アパートの事故物件の売却相場
事故物件のアパートの売却相場は、資産価値の5〜9割ほどになります。
売却相場は、事故物件となった原因により異なります。孤独死は資産価値の1〜2割ほど低下する一方、他殺は3〜5割低下する場合があります。
参照元:ハッピープランニングHP(https://happyplanning.jp/column/2691/)
事故物件となったアパートを売却するポイント
特殊清掃・リフォームで綺麗に
事故発生後の部屋は、まず「再び人が住める状態」に整えることが出発点となります。特殊清掃で臭いや汚れを除去し、衛生的な環境を取り戻しましょう。そのうえで、クロスや床材を張り替えるなど軽いリフォームを行えば、印象が大きく変わります。
外観や共用部の清掃も合わせて実施すれば、内見時の印象も向上。心理的な抵抗をやわらげる効果も期待できるでしょう。
一定の期間を空ける
事故後すぐに売却を進めると、地域内での印象が残っていることもあり、買主が見つかりにくいこともあります。そのため、場合によっては一定の期間を空けた上で売却活動を始めることも、現実的な選択肢の一つとなるでしょう。
時間を空けている間に、清掃や改修、必要書類の整理を進めておけば、次の手続きもスムーズになります。焦らずタイミングを見極めることが、売却価格の安定にもつながるでしょう。
更地にする・建て替える
建物の印象を一新したい場合は、解体して更地にするか、または建て替えするという方法も有効な選択肢。古い建物のままでは事故の印象が残りやすいため、買主が敬遠する可能性があるからです。更地として売却すれば、建物の心理的瑕疵を理由にした値引き交渉を避けられる場合もあるでしょう。
ただし、解体や新築には費用がかかるため、売却見込み価格との支出とのバランスを慎重に見極めることが大切です。
事故物件の買取業者に依頼する
自力で買手を探すのが難しい場合は、事故物件の買取を専門とする業者に相談する事も有効です。
これらの業者は心理的瑕疵物件への理解が深いため、一般的な仲介よりも短期間で売却が完了することが多いのが特徴。価格は相場より下がる傾向があるものの、現金化までのスピードや手間の少なさを重視する方には適した選択肢です。「とにかく早く手放して、次の物件でリセットしたい」という方は、すぐにでも専門の買取業者へ相談するようおすすめします。
アパートの事故物件の売却に関するQ&A
Q.事故物件の売却に死亡診断書は必要ですか?
A.売却手続きそのものに、死亡診断書の提出が義務づけられているわけではありません。ただし、事故発生の有無や経緯を確認するために、不動産会社や買取業者から提示を求められるケースもあります。
その際は、死因や個人情報を除いた写しを提出するのが一般的。法的義務ではなく、取引の透明性を保つための確認プロセスという位置づけです。
Q.入居者が自殺した場合に損害賠償は請求できますか?
A.入居者が室内で自殺した場合、オーナーは経済的・精神的な損失を受けることがあります。このようなケースでは、遺族に対して損害賠償を請求できる可能性がありますが、実際に認められるかどうかは状況次第。たとえば、遺族に支払い能力がない場合や、本人の責任が明確でない場合には請求が難しくなることもあります。
請求内容としては、原状回復費用や特殊清掃費、空室期間中の家賃損失などが一般的です。感情的な対立に発展しやすいため、弁護士など専門家を通じた対応が望ましいでしょう。
実際の請求可否は、契約内容や事故の経緯を踏まえて慎重に判断されることとなります。
Q.遠方に住んでいて立ち会えなくても手続きは可能ですか?
A.遠方に住んでいても、現地に行かずに事故物件の売却を進めることは可能です。不動産会社に委任状を提出すれば、現地確認や契約手続きを代理で行ってもらえます。
必要書類を郵送で、相談をオンラインで行なえばリモートのみで売却が完結。売却後の清算も郵送や振込で進められるため、距離が障害になることはほとんどありません。
まとめ
アパートが事故物件となっても、売却自体は可能です。ただし、価格の下落や告知義務など、一般の取引にはない要素もある点を理解しておきましょう。
心理的瑕疵の扱いや買主への説明を誤ると、後々のトラブルにつながる可能性があります。トラブルを避けるためには、事故物件の扱いに詳しい専門家へ相談し、状況に合った売却方法を選ぶことが重要です。