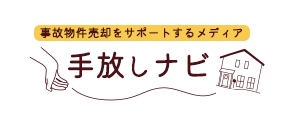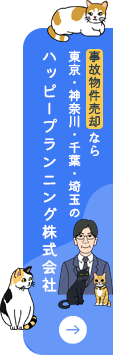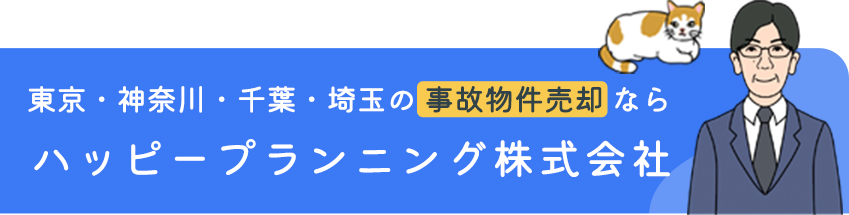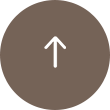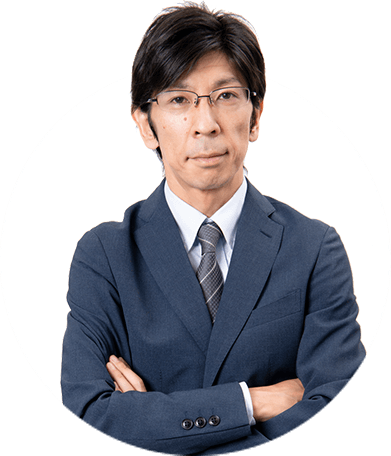
『ハッピープランニング株式会社』代表
相談実績が豊富な、
事故物件対応のプロフェッショナル。
家族が自死した住まい(事故物件)を相続した場合、相続登記などの手続きが必要です。もし手放したい場合は相続放棄する手段もありますが、相続放棄はデメリットが少なくありません。可能なら売却も検討しましょう。
ここでは、家族が自死した住まいを相続するべきかどうかの判断基準や、相続後の選択肢などをご紹介します。
事故物件の定義
事故物件とは、主に事件や事故によって人が死亡した不動産を指します。自死や他殺のほか、状況によっては孤独死・火災で人が死亡した場合も事故物件になることがあります。
これらは心理的瑕疵がある物件とされ、売却時には告知義務が発生します。
このほか、不動産の瑕疵には物理的瑕疵や法律的瑕疵などがあります。一般に事故物件とはみなされませんが、告知義務の対象となります。不動産の価値にも関わるため注意しておきましょう。
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
事故物件とは、人の死が関連して心理的な抵抗を感じる可能性のある不動産のことを言います。
国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」により、その定義が明確化されました。自殺や他殺など心理的瑕疵(かし)がある物件はもちろん、事故死や自然死であっても特殊清掃が実施された場合は、事故物件として扱われています。
一方で、老衰や病死などの自然死、不慮の事故死、隣接する住戸や通常使用しない共用部での死亡が関連する物件については、事故物件とはみなされず告知義務の対象外となります(特殊清掃が行なわれていない場合)。
心理的瑕疵がある物件
心理的瑕疵のある物件は、住むことに対して心理的な抵抗がある不動産をいいます。先に触れた事故物件はもちろん、近隣に墓地・火葬場などの施設がある場合や、近隣に指定暴力団の構成員が居住している場合なども該当します。
心理的瑕疵は目に見えないため、感じ方は人それぞれです。しかし住まうための心理的な抵抗が大きく、避けられる傾向があります。不動産取引では告知義務の対象となるため、入居者・購入希望者に対する正確な情報の提供が求められます。
物理的瑕疵がある物件
物理的瑕疵がある物件は、土地・建物に不具合や欠陥がある不動産をいいます。
居住に問題のある物件がほとんどで、主に以下のような欠陥を抱えています。
- 建物の傾き
- シロアリ
- 雨漏り
- 耐震強度不足
- 土壌汚染
- 設備の不具合・故障
このほか、地中の障害物や軟弱地盤なども物理的瑕疵に該当します。自死が発生した事故物件であっても、何らかの物理的瑕疵が発生する可能性があります。不安がある方は、不動産業者に住宅を診断してもらいましょう。
法律的瑕疵がある物件
法律的瑕疵がある物件は、法律・条例によって何らかの制約が発生している不動産のことです。
例えば、以下に該当する不動産は法律的瑕疵のある物件といえます。
- 違法建築物
- 接道義務を満たしていない
- 市街化調整区域の制限を受けている
- 所有権や抵当権があいまい
法律的瑕疵のある物件は自由な利用が難しく、不動産の売買にも影響することがあります。
売却時は不動産業者に相談し、適切なアドバイス・サポートを受けましょう。
事故物件の相続税評価は
どうなる?
事故物件でも相続税は
変わらない
相続税の評価額は、事故物件であっても通常の不動産と変わりません。事故物件は心理的瑕疵がありますが、影響が及ぶのは不動産取引のみです。不動産の相続税評価は路線価を基準とするため心理的瑕疵の有無は影響しません。
例えば、事故物件の相続税評価額が2,000万円だとしても、不動産業者の査定額が1,500万円になることはあります。
業者による事故物件の査定額と、相続税評価額は別物ですので、混同しないように注意しましょう。
相続人の範囲と法定相続分
事故物件の相続人は、自死した故人(被相続人)の配偶者や子ども、親族や兄弟姉妹が該当します。相続の優先順位は次のとおりです。
- 配偶者
- 子ども
- 親
- 兄弟姉妹
相続順位は配偶者が高く、次いで子ども、親、兄弟姉妹となります。なお、代理人(代襲相続人)も同様の順位で相続権があります。
法定相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を実施して事故物件の取扱を決めることが大切です。
財産を相続する場合、遺言書や遺産分割協議の内容に従って分割する方法が一般的です。一方、法定相続分に沿って分割する手段もあります。法定相続分は、相続人の相続割合のことで、相続人数や被相続人との続柄により変わります。
遺言書で指定がない時は、法定相続分に沿って財産を分割することも検討が必要です。
相続税額の計算方法
相続税を計算する場合、まずは相続人数を確定させましょう。相続人数によって控除額が変わるため、相続税額が変動します。
相続人数が確定したら、以下の流れで計算を行います。
- 相続対象の財産を洗い出す
- 専門家に事故物件の鑑定などを依頼し、
財産の価値を確定させる - 被相続人の負債(ローンなどの借金)と
葬儀費用を確定させる - 相続対象の財産額から負債・葬儀費用を
差し引く - 相続人一人ひとりの財産額を確定させる
- 相続した財産額から控除を差し引く
相続財産額から控除を差し引き、0またはマイナスになった場合は相続税がかかりません。
相続税の控除額は、基礎控除が3,000万円、相続人1人につき600万円です。相続人が3人の場合、控除額は4,800万円となります。相続した財産額が4,800万円以下の場合、相続税は課税されません。
相続税の税率は、控除後の金額によって異なります。累進課税のため、相続した財産が多いほど相続税額も高くなります。
事故物件を相続した際の
法的手続き
相続登記の実施
事故物件を相続した場合、最初に行わなくてはいけない手続きが相続登記です。相続登記は、相続した不動産の名義を変更する手続きをいいます。相続人が不動産の所有者であると証明するために必要で、不動産の取引にも影響します。
相続登記を行うためには、被相続人や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書など、多数の書類を揃えなくてはいけません。手間と時間がかかりますが、司法書士など専門家に依頼することでスムーズに手続きできます。
なお、相続登記には登録免許税と書類の発行費用、司法書士費用などがかかります。
相続登記は、不動産の相続を知った日か遺産分割協議から3年以内に手続きする必要があります。義務化されていますので、忘れないうちに手続きするか、司法書士に相談しましょう。
(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/2.html)
固定資産税の確認
事故物件を相続した際は、固定資産税もチェックしておきましょう。固定資産税は、主に土地や建物などの不動産に対して課税される税金です。事故物件も固定資産税が課税されるため、相続後は期限までに支払う義務が発生します。固定資産税を納める人は、主に対象の不動産の所有者です。事故物件を相続した場合、相続人が固定資産税を納める必要があります。
固定資産税は路線価を基準に税額を決めていますが、戸建やアパート・マンションなどは特例措置で税金が軽減されます。
ただし、住宅を解体して更地にした場合など、固定資産税が高くなってしまうケースもあります。事故物件を相続した時は、固定資産税分の資金を確保するとともに、取り扱い方法を決めておきましょう。
告知義務の理解
事故物件を売却したり賃貸に回したりする場合、告知義務が発生することを押さえておきましょう。心理的瑕疵のある不動産は、入居希望者や購入希望者に対して事故物件である事実を開示する必要があります。これを告知義務といい、不動産取引では瑕疵のある物件が対象になっています。
告知義務を怠ると、不動産の取引契約が無効になったり、相手から慰謝料を請求されたりする可能性があります。他のトラブルが発生するリスクもあるため、告知義務に沿った適切な取引が求められます。トラブル防止の観点からも、取引を行う不動産業者や、法律に詳しい弁護士へ相談し、告知義務の正確な把握と理解に努めましょう。
事故物件は相続するべき?
判断基準について

まず相続する不動産に、どれぐらい資産価値があるのか査定を依頼しましょう。
相続するか放棄するかは、自死があったとしても、被相続人が残した負債よりも不動産に資産価値があると分かれば相続をしていいと思います。財産目録も作成し、相続するべきか否か、親族と法律関係の専門家を交えて相談するといいでしょう。
また、現在住んでいるご自宅でご家族の自死があった場合、気持ちの面で落ち着かないことがあると思いますので、身近な人や話しやすい方に相談をして不安を少しでも解消しましょう。
相続を検討した方が良い
ケース
負債よりも財産の額が多い
もし負債よりも財産の額が上回る場合、事故物件を含めて相続を検討したほうがよいでしょう。相続では借金などのマイナス財産も相続対象になりますが、他の財産と合わせてプラスになるなら、相続放棄は避けるべきといえます。相続放棄を行うと、現金や預金、貴金属など価値のある財産も相続不可能になるためです。
相続放棄が決まってしまうと、いかなる手段でも取り消しできません。財産の額が多い場合、後悔しないように慎重に相続可否を判断しましょう。
資産価値が低い・売却が困難
事故物件は、購入希望者が心理的な不安を抱きやすいため、一般的な物件よりも敬遠される傾向にあります。
結果、市場での評価が下がりやすく、売却価格も通常より低めであることが一般的。買い手も限られることから、売却までの期間が長引くことも少なくありません。
そのため早期の売却を希望する場合には、事故物件の取扱いに慣れた専門業者へ相談するケースが増えています。
手放したくない財産がある
手放したくない・思い入れの強い財産がある場合も相続を検討しましょう。相続放棄してしまうと、後悔する可能性が高いと考えられます。相続放棄は、全財産の相続権を失う手続きです。そのため、特定の財産のみを相続することはできません。
不要な財産がある場合は、他の相続人と話し合うことが大切です。事故物件だけを手放したい時は、いったん全ての財産を相続し、落ち着いてから売却するなど別の手段を検討しましょう。
トラブルなく遺産分割協議が完了した
遺産分割協議がスムーズにまとまった・まとまりそうな時は、相続放棄をする必要性が薄いといえます。協議に従って財産を相続するだけですので、相続放棄を行うメリットはありません。遺言書に沿って財産を分割するケースも同様で、トラブルがなければ相続を検討したほうがよいでしょう。
相続放棄は、相続でトラブルになった時などの最終手段の一つです。問題なく財産を相続できるのであれば、遺産分割協議に沿って対応することをおすすめします。
相続放棄を検討した方が良い
ケース
負債が多い(債務超過)の状態
現金や預金などの財産よりも借金や負債が多い(債務超過の状態)場合、相続放棄も検討する余地があります。相続では負債も対象になりますので、相続人は借金やローンを返済する義務が生じます。自分自身が負債に悩まされるリスクがあるほか、私生活に影響が及ぶ可能性も否定できません。
負債の金額にもよりますが、相続した財産を処分しても多額の負債が残る時は相続放棄も一つの選択肢です。家庭裁判所への申立も検討しましょう。
相続トラブルに巻き込まれたくない
相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合、相続放棄も選択肢の一つに入れておきましょう。複数の相続人がいると、誰がどの財産を相続するのか揉めることが多く、裁判にまで発展するケースも見られます。問題が長期化するリスクもありますが、相続放棄すればトラブルに巻き込まれることはありません。
ただし、プラスの財産も相続できないほか、他の相続人の負担が大きくなります。また、相続放棄により他の相続人との関係が悪化するなど、別のトラブルが発生する可能性もあります。
財産を特定の相続人に集中させたい
少々特殊ですが、財産を特定の相続人へ集中させたいときも相続放棄が選択肢に入ります。例えば、家業を継ぐ人物に事業用の財産を相続させたいケースなどです。相続放棄すると、財産は他の相続人に引き継がれますので、1人に全財産を相続させることも可能です。
しかし、負債がある場合は特定の相続人に負担が集中します。もし相続人の返済が滞った場合、相続放棄した人物に請求が来る可能性もあります。
相続放棄とは?注意点
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切引き継がないと決める法的手続きのこと。借金などの負債を受け継ぎたくない場合に有効ですが、被相続人が持つすべての財産を放棄する必要がある点に注意が必要です。
すべての財産
相続放棄とは、特定の財産だけを手放す手続きではなく、相続する権利そのものを放棄する手続きとなります。
故人に多くの借金がある場合に選択されることの多い手続きですが、相続する権利そのものを放棄する以上、故人の預貯金や不動産、株式などのプラスの財産も放棄しなければなりません。仮に、事故物件など価値の低い不動産を避けるために相続放棄した場合、他のプラス財産も一切受け取れなくなる点に注意が必要です。
相続放棄で損をしないためには、故人の全体の資産状況をしっかりと確認することが重要。放棄の可能性を検討する際は、弁護士や司法書士など専門家へ相談すると安心でしょう。
申請期限
相続放棄の申請は、相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ行う必要があります。この期間内に「相続放棄申述書」を提出しなければ、すべての財産を承継したものとみなされる仕組みです。
もし期間内に遺品整理や不動産の処分を行うと、相続を承認したと判断される場合があるため、手続き前には慎重な対応が求められます。
なお、期限に間に合わない場合や判断できない状況の場合、「限定承認」や「熟慮期間の延長」を申し立てる方法も選択できます。
管理責任
相続放棄をしても、手続きが完了するまでは財産の管理責任が残ります。特に建物や土地などの不動産がある場合、損壊や火災などの被害が出ないよう一定の管理を行わなけれななりません。
仮に、自分以外の相続人が決まるまで不動産を放置した場合、近隣トラブルや行政処分の対象となることもあるため注意が必要です。
なお、相続放棄後に誰も管理しない状況が続く場合には、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることが可能ですが、まずは管理責任を怠らないことが余計なトラブルを防ぐ第一歩といえるでしょう。
事故物件を相続放棄するには?手続き方法を解説
(1) 家庭裁判所への申立て
事故物件を相続放棄したい場合家庭裁判所への申立てを行いましょう。家庭裁判所への申立ては、相続人本人が行う必要がありますが、弁護士・司法書士など専門家への依頼も可能です。相続人が未成年の場合、親が法定代理人として申し立てることもできます。
相続放棄を行う際は、相続放棄申述書の作成が必要です。弁護士・司法書士へ依頼する際は別途費用がかかります。実費が発生するケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
必要書類
相続放棄を行う際は以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票か戸籍附票
- 相続放棄を行う人(申述人)の戸籍謄本
- 血縁者の戸籍謄本(一部該当する申述人のみ)
相続放棄申述書のほか、被相続人の戸籍謄本や住民票除票(または戸籍附票)が必要です。相続放棄を申し立てる本人の戸籍謄本も集めましょう。
戸籍謄本は、本籍地にある市区町村役場の窓口で発行可能です。住民票除票は、前の住所地の市区町村役場で取得します。各書類は、弁護士や司法書士に取得を代行してもらうことも可能です。
(2) 申立て後の確認
相続放棄申述書と書類を揃えたら、家庭裁判所へ提出しましょう。提出後、しばらく経つと家庭裁判所から申述人あてに照会書が届きます。照会書は、相続放棄に関する複数の質問事項が記載されている書類です。定められた期限までに回答し、返送する必要があります。
照会書は、相続放棄の最終的な意思確認の意味も含まれますので、手続きするかどうか再判断しましょう。相続放棄をする場合は照会書の質問事項を記入し、返送すれば問題ありません。
(3) 相続放棄の通知
照会書を返送後、家庭裁判所で回答内容が審査されます。相続放棄が適切と判断された場合、相続放棄申述受理通知書が郵送で届きます。封を開け、相続放棄ができていることを確認しましょう。
もし照会書の記載内容に不備があった時は、家庭裁判所から通知が届くこともあります。指摘された内容に沿って適切に対応しましょう。
事故物件を相続する場合は?注意点を解説
事故物件を相続する際には、以下の点に注意しましょう。
専門家への相談
事故物件を相続した時は、相続に強い弁護士や不動産業者などの専門家に相談しましょう。相続後の適切な取り扱い方法は、個々のケースによって異なります。プロの視点から適切な対応策をアドバイスしてもらいましょう。
感情面の整理
必要な手続きが一段落したら、感情面を整理することも大切です。事故物件は事情が特別なため、心理的な負担は決して小さくありません。家族はもちろん、必要であればカウンセラーにも相談してメンタルをケアしましょう。
事故物件相続後の選択肢
保有して賃貸に出す
事故物件を相続した場合、賃貸として運用する方法もあります。事故物件は需要が限られるものの、賃貸に出せば家賃収入を得られます。物件を手放す必要もなくなりますので、諸事情で売却できず、居住することも難しい時は検討の余地があります。
メリット
事故物件を賃貸に出すと、入居者がいる限りは継続的な家賃収入が得られます。該当する部屋のリフォームやリノベーションを行えば、心理的な抵抗も和らげることが可能です。
デメリット
事故物件は、入居希望者に対する告知義務があります。事実を隠して入居者を募集することはできません。
心理的な抵抗も強いため、入居者が見つかるまでに時間がかかる可能性があります。
そのまま居住する
事故物件の特殊清掃やリフォームを行い、そのまま居住することも選択肢の一つです。思い入れのある住まいや、賃貸に回したくない・売却したくない時に適しています。
そのまま居住する場合も相続登記は必須ですので、早めに手続きしておきましょう。
メリット
事故物件に居住する場合は、必要な手続きが最小限で済みます。特殊清掃や相続登記などの手続きのみで済む一方、相続放棄や不動産業者への相談は不要です。
デメリット
そのまま居住する場合、特殊清掃は必須と考えておきましょう。特殊清掃のみで原状回復が難しい時は、リフォームも検討が必要です。
居住にかかる費用が膨らまないように注意しましょう。
売却する
事故物件を手放したい時は売却を検討しましょう。賃貸での運用が難しい物件や、所有を続ける理由がない場合に適しています。
事故物件は需要が限られますが、売却することも不可能ではありません。事故物件の取り扱いが可能な不動産業者もあるため、一度相談してみましょう。
メリット
事故物件を売却すれば、維持管理にかかる負担を減らせます。定期的な物件のメンテナンスや修理・修繕が不要になるため、金銭面・心理面ともに負担を軽減可能です。
デメリット
事故物件を売却するデメリットは、相場よりも価値が低くなってしまう点にあります。物件の状態や立地にもよりますが、市場価格から数割ほど下がると考えておきましょう。
事故物件の相続に関するQ&A
Q.相続するか否かいつまでに決めればいいですか?
A.回答
相続するか放棄するかの判断は、「相続が開始したことを知った日から3か月以内」に行う必要があります。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄や限定承認の申立てを行わなければ、すべての財産を承継する「単純承認」とみなされる仕組みです。
なお、裁判所から相続放棄や限定承認が認められる前に遺品整理や不動産の処分などを行うと、相続を単純承認したと判断される恐れもあるのでご注意ください。
もし財産の内容を把握しきれない場合には、「熟慮期間の延長」を申し立てることで判断の猶予を得ることが可能です。早めに家庭裁判所や専門家へ相談すると安心でしょう。
Q.相続人が相次いで相続を放棄するとどうなりますか?
A.回答
相続放棄は、放棄した人に代わって次の順位の相続人へ権利が移る仕組みになります。たとえば配偶者や子が放棄した場合、次に親や兄弟姉妹が相続人となります。さらにその人たちも放棄すれば、甥や姪など、より遠い親族へと順番に権利が移動していく流れです。
最終的にすべての相続人が放棄すると「相続人不存在」となり、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任して財産を管理・処分することになります。
事故物件など処分しづらい不動産が相続財産として残った場合、固定資産税などの費用だけが膨らむケースもあります。できるだけ早い段階で専門家へ相談することが望ましいでしょう。
Q.事故物件であることはバレますか?
A.回答
事故物件の売却時には、宅地建物取引業者が買主への「告知義務」を負うため、基本的に隠すことはできません。自殺や他殺など心理的瑕疵がある場合には、契約前にその事実を買主へ説明する必要があります。
仮に告知せず事故物件を売却できたとしても、近隣住民の話や過去の居住履歴、インターネット上の事故物件情報サイトなどから、多くの場合は事故物件であることが判明します。判明した場合、買主からの損害賠償請求へ発展する恐れもあるので、正直に情報を開示することが重要です。事故物件の取り扱いに慣れた業者へ相談することが安全です。
Q.建物を更地にすることはできますか?
A.回答
相続人として所有権を取得した後であれば、建物を解体して更地にすることは可能です。ただし建物を取り壊しても、「過去に死亡事案があった土地」として心理的瑕疵が残る場合があり、完全に事故物件の印象を消すことは難しいとされています。
また、建物をなくして更地にすると固定資産税の負担が増えるため、解体費用や売却計画を含めて総合的に判断することが大切です。事故物件の買取に強い専門業者へ相談すれば、解体せず現状のまま売却できる場合もあります。
事故物件の売却方法
仲介業者に依頼
事故物件を高く売却したい時は、仲介業者へ依頼する選択肢があります。仲介は、業者に事故物件の購入希望者(買い手)を探してもらう不動産の売却方法です。宣伝などの販売活動は業者が行うため、基本的に任せきりで問題ありません。売買に関する交渉もサポートが受けられます。
事故物件は需要が限られるため、買い手探しに時間がかかる可能性があります。どの程度で売れるかはケースバイケースですので、すぐ手放したい方には不向きの方法といえます。
買い取り業者に依頼
事故物件を早めに手放したい時は、業者による買い取りが選択肢に入ります。買い取りは、業者に直接対象の不動産を売却する方法です。買い手探しが不要なため、スピーディな売却を実現できます。事故物件を短期間で手放せますので、時間をかけたくない方に適した売却方法です。
不動産の買い取りは、仲介と比較して価格が安くなることがあります。判断に迷った時は、業者に適切な方法を提案してもらいましょう。
事故物件を手放すなら、
事故物件専門の
買い取り業者へ相談を
事故物件を確実に手放したい場合、事故物件の買い取りに強い専門業者へ相談しましょう。専門業者は事故物件の取扱実績が多いため、売却時に手厚いサポートを受けられます。特に事故物件は通常の不動産とは事情が異なりますので、経験豊かな専門業者は心強い存在となります。
買い取りであれば、売却後に何らかの瑕疵があっても責任を負う必要はありません。告知やトラブル対応は業者が行うため、売却後の負担も軽減することが可能です。