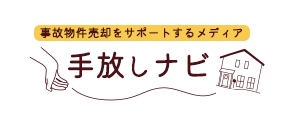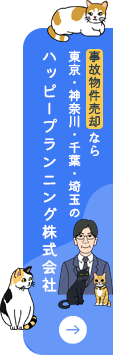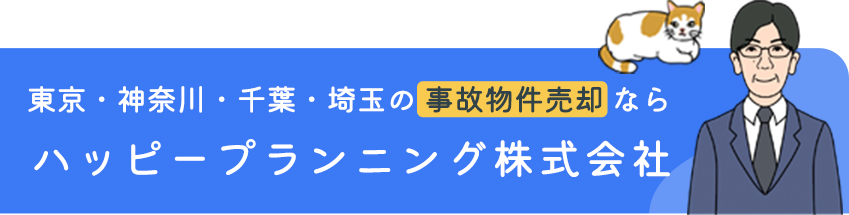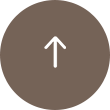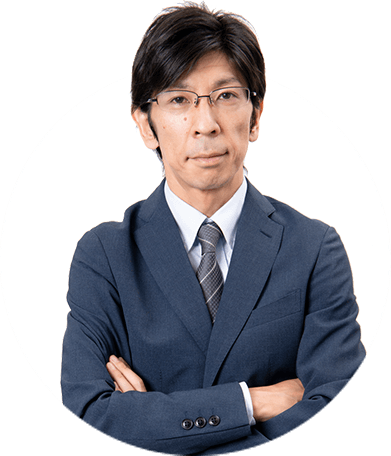火災によって建物が損傷すると、たとえ人が亡くなっていなくても事故物件とみなされるケースがあります。事故物件となった建物でも、特に規制の縛りを受けることなく売却が可能ですが、買主に対して告知義務を負うこと、市場価格より安い金額で成約する可能性が高いことは理解しておかなければなりません。
火災は事故物件に該当する?
火災が起きたからといって、すべての物件が事故物件になるわけではありません。判断基準となるのは、火事の規模や被害内容、居住者や周辺への影響など。たとえば台所の一部を焦がした程度のボヤや、建物構造に損傷がない小規模な火災なら事故物件とはみなされないのが一般的です。
一方、建物の一部が焼失したり人の死亡を伴う火災が起きた場合には、心理的な抵抗を与える要因とされ、事故物件に該当する可能性が高まります。これらの判断には専門的な知識が必要となるため、所有者が自己判断で結論を出して売却活動を始めるのはハイリスク。弁護士や事故物件の取り扱いに詳しい不動産会社へ相談し、客観的な見解を得ることをおすすめします。
事故物件は「告知義務」がある
火災の程度や被害状況、人の死の有無などにもよりますが、火災があった建物は「心理的瑕疵(しんりてきかし)」があると判断されることがあります。
心理的瑕疵とは、建物の利用自体には問題がなくても、購入者や借主が知ると不安や抵抗を感じる可能性のある事情のこと。たとえば火災で人が亡くなった建物や焼損後に再建した履歴が残る建物などは、買主に対してその内容を正直に説明しなければなりません。
なお、告知義務があるからといって売却が不可能になるわけではなく、誠実に説明することで取引は成立します。ただし事実を意図的に隠した場合には「契約不適合責任」などを問われ、損害賠償や契約解除に発展するおそれがある点にご注意ください。
国土交通省が示すガイドラインを確認し、告知の範囲をあらかじめ把握しておくことが大切です。
参照元:国土交通省[PDF](https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)
火事の告知義務の期限
火災に関する告知義務は、永久に続くわけではありません。国のガイドラインでは、買主が心理的な抵抗を受けるかどうかを基準とし、個別事情に応じて告知義務期間が決まります。
たとえば火災発生から長期間が経過し、再建後に新たな入居者が問題なく生活しているような場合は、心理的瑕疵の影響が薄れたと判断されるでしょう。
ただし人が亡くなった火災では、年月が経っても心理的抵抗が残るケースも多いことから、個別での判断が必要になります。判断に迷う場合は、不動産会社や弁護士に相談して適切な対応を確認しましょう。
火事は”隠れた瑕疵”に注意
火災後の建物には、外から見ただけでは分からない損傷や不具合が残っていることがあります。こうした問題は「瑕疵(かし)」と呼ばれ、放置すると売却後のトラブルにつながりかねません。
特に注意すべきは、火災による「物理的瑕疵」と、見えない部分に残る「隠れた瑕疵」。それぞれの特徴を把握し、売却前にしっかり確認しておきましょう。
物理的な瑕疵
火災によって建物の構造や設備が損傷した場合、それは「物理的瑕疵」とされます。柱や梁の焦げ、断熱材の劣化、配線や配管の焼損など、表面上は修復されていても内部で影響が残っているケースは少なくありません。
きちんとした修繕や確認を怠ったまま売却すると、後に買主から損害賠償を求められるリスクもあります。専門業者に調査を依頼し、状態を明確にしておくことが重要です。
隠れた瑕疵
火災後、見た目がきれいに整っていても、内部に「隠れた瑕疵」が残ることがあります。煙や焦げの臭いが壁材や床下に染み込んでいたり、化学物質が残留していたりするケースなどで。
入居後に不快感や健康被害を訴えられることもあるため、売却前に十分な点検が必要でしょう。専門家の診断で臭気や汚染の有無を確認し、必要に応じて除去・改修を行うことをおすすめします。
火災による事故物件の売却価格は?
火災による事故物件の売却価格は、建物の損傷状況や再建の可否によって大きく異なります。部分的な焼損で修復が可能な場合は、一般的な相場の5~7割程度で売却できるケースもあるでしょう。
一方、全焼や人の死亡を伴う火災では建物の価値がほぼなくなり、土地のみが査定対象となる傾向があります。その際は解体費や撤去費を差し引いた金額が実際の売却価格となるため、相場より下がる例も少なくありません。
複数業者の査定を受け、現実的な価格を把握しておきましょう。
火災による事故物件は修復すべき?
火災で損傷した物件を売却する際は、修復してから売るか、現状のまま売るかを見極めることが重要です。修復して売る場合は建物の印象が改善され、一般市場での買い手も見込みやすくなります。ただし修繕費が高額になりやすく、費用を販売価格で回収できるとは限りません。
一方、修復せずにそのまま売る方法は、工期をかけずに早期売却できる点が利点。しかし見た目の損傷や臭いが残ると買い手が限られ、売却価格が大幅に下がる可能性があります。また内部の損傷や説明不足が、後の契約不適合責任につながるリスクにも注意が必要です。
費用とリスクを整理し、複数業者に相談して最適な判断を行いましょう。
火災による事故物件を売却するポイント
解体・建て替えで土地の価値を再生する
火災による損傷が大きい場合は、建物を解体して更地にする方法と新たに建て替える方法があります。更地にすれば心理的な抵抗が薄れるため、買い手が見つかりやすくなる可能性があるでしょう。一方、建て替えを行えば再利用可能な物件として売却できるため、相場に近い価格での取引が期待できます。
ただし解体費や建築費が高額になることもあるため、費用対効果を比較して判断することが大切です。
土地の用途を変えて再活用する
火災で建物を失っても、土地の活用方法を変えることで資産として再生できます。たとえば駐車場や資材置き場など、建物を建てずに運用する方法なら、初期費用を抑えつつ継続的な収益を得ることが可能。建築コストをかけずに維持できるため、再建に踏み切れない場合の一時的な活用にも適しています。立地条件に合わせ、売却と運用の両方を比較検討してみると良いでしょう。
事故物件専門の買取業者へ相談する
火災による事故物件を早く手放したい場合は、専門の買取業者に依頼する方法が有効です。一般の不動産会社では買い手が見つかりにくいケースでも、訳あり物件を専門に扱う業者なら、現状のまま買い取ってもらえる可能性があります。
修復や解体の手間が省け、短期間で現金化できる点は買取業者を利用する大きなメリット。ただし相場より価格は下がる傾向があるため、複数業者に査定を依頼して比較することが大切です。
まとめ
火災による事故物件は、被害の内容や程度によって取るべき対応が異なります。修復や更地化、用途変更、土地活用など、状況に応じた方法を比較検討するようにしましょう。
売却を主軸に進める場合、判断を誤ると契約トラブルにつながるおそれもあるため、経験豊富な専門業者へ早めに相談し、最適な手放し方を見極めることが大切です。