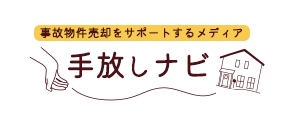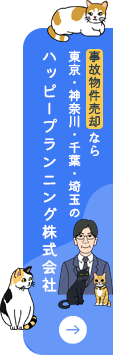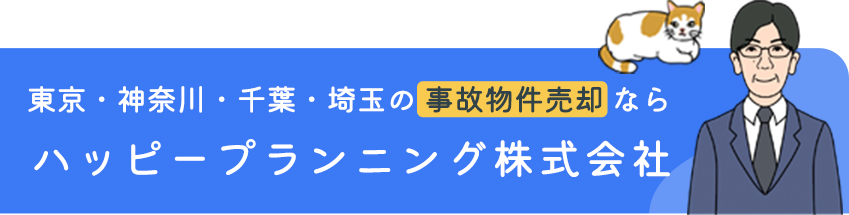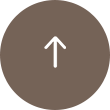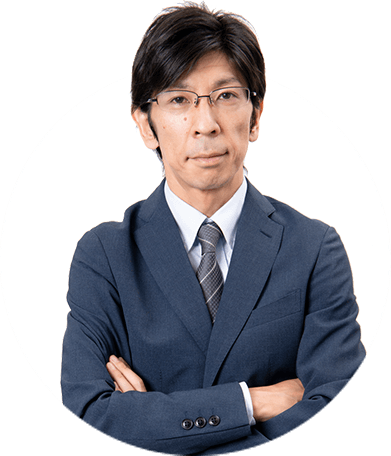事件や事故の影響から、心理的に避けられやすくなる事故物件。心理的瑕疵があるため、売却には注意を要する不動産です。
ここでは、事故物件の定義や告知義務、市場での取引相場など、事故物件の売却に欠かせない基礎知識をまとめています。
事故物件とは
事故物件の定義
事故物件は、自死や他殺などの事故・事件、孤独死などによって人が死亡したことのある不動産の総称です。2021年には国土交通省がガイドラインを策定しました。入居・購入に影響する心理的瑕疵があるため、賃貸・売買などの取引を行う際の告知義務が課せられています。
事故物件は心理的に避けられる傾向が強く、通常の不動産よりも資産価値が低くなります。手放す際は売却方法を検討し、事故物件の取扱実績豊富な業者に相談することが重要です
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)
どこまでが事故物件に
該当する?
事故物件は、主に自死や他殺が行われた不動産が該当します。孤独死も事故物件に該当しますが、発見状況によっては対象外となります。孤独死の場合、特殊清掃が必要なケースなどに限られます。
マンションなどの集合住宅は、共有部で起きた事案によって事故物件となるケースがあります。ただし日常利用しない共有部で発生した事案は対象外です。
事故物件の売却方法
事故物件の売却方法は、大別して仲介と買い取りがあります。
仲介は、不動産業者に物件の購入希望者を探してもらう方法です。買い取りは、業者に物件を直接売却する方法をいいます。
仲介は購入希望者が探す必要があり、売却できない可能性もあるため、事故物件の場合は確実・スピーディに売却できる買い取りがおすすめです。
事故物件の売却相場
事故物件の売却相場は、事件・事故などの原因によって異なります。孤独死の場合は資産価値の2~5割減ほどですが、自死は資産価値の3~7割減となることがあります。他殺は価値の下落が大きく、売却相場は資産価値の5〜8割減が目安となります。事故物件を高く売りたい場合、リフォームや特殊清掃を行うか、業者に買い取りを依頼しましょう。
事故物件の告知義務
告知義務は、不動産の入居・購入希望者に不具合・欠陥などの情報を伝える義務のことです。事故物件は心理的瑕疵が生じるため、取引時には事実を伝える必要があります。賃貸取引の場合、告知義務は3年と期間が定められています。一方、売買取引は期間の定めがありません。事案発生から3年以上が経った場合でも告知義務が残ります。
事故物件の特殊清掃は
必要か
特殊清掃は、事件・事故の発生現場で殺菌・消毒や脱臭などを行う専門的な清掃をいいます。事故物件は特殊清掃がほぼ必須ですので、売却前に業者に依頼しておきましょう。
特殊清掃は費用がかかるものの、事件や事故の痕跡を消すことが可能です。心理的な抵抗感も緩和できるため、売却しやすくなるメリットもあります。
事故物件のお祓い
効果・費用
事故物件はお祓いせずとも売却可能ですが、なるべく行っておきましょう。お祓いは日本の日常的な慣習のため、心理的な抵抗感を和らげることに繋がります。特殊清掃を行う前か、売却前に近隣の寺社へ相談してみましょう。
お祓いの費用相場は依頼先や地域によって異なります。なお、お祓い後も告知義務は残るので注意しましょう。
事故物件の残置物処理は必要か
事故物件における残置物処理は自分でするか業者に依頼するかでそれぞれメリット・デメリットがあります。また、残置物の所有権は相続人が相続する事になる点にも注意が必要であり、相続放棄や処分・原状回復の費用負担などの兼ね合いも知っておきましょう。
事故物件ロンダリング
事故物件の告知義務期間である3年の間、一時的・短期的な入居者に貸し、次の入居者への告知義務を回避することを、事故物件ロンダリングといいます。不動産業界の一部で行われている慣習ですが、事故物件ロンダリングを正当化する法的根拠はまったくありません。
事故物件の保険
事故物件にはさまざまなリスクが伴いますので、いざというときのために備えておくことが重要です。「家主型孤独死保険」や「入居者型孤独死保険」のほか、火災保険などで備えておくことが可能ですので、検討してみてはいかがでしょうか。
事故物件の遺品整理
事故物件において遺品整理は切っても切り離せない関連性があります。基本的には相続人である遺族が対応することが通常ですが、もし遺族と連絡が取れない場合にはオーナーが自ら対応しなければならないことがあります。